外科医には、さまざまな「掟(おきて)」がある。掟というと、決まりきったお作法と思いがちだが、本来そこには「理論」があるはずだ。本書は、外科専攻医の目線で、一人前の外科になるために必要な「掟」について再考し、深堀りし、その背景にある理論について考えていく。著者が過去に指導した外科専攻医「ドラゴン」が主人公となり、臨床現場で遭遇する様々な事例について体当たりで考えて、成長していく過程を書籍にまとめた。外科医だけでなく周術期に関わる全ての医療者にとって役立つ、リアルな臨場感あふれる教科書。
書籍の概要:序章より
手術をやらせたくなる専攻医になろう
「おはよう! 術後の患者さんどう?」
この質問こそ、外科専攻医への「キラークエスチョン」であろう。朝一番に顔を合わせた時、専攻医からの回答は実に様々である。温度板と採血データしか診ていない者、ナースの申し送りの伝言ゲームを始める者、何から伝えるべきか分からずうろたえる者、大丈夫ですとだけ答える者、中には「どの患者のことでしょう?」と逆質問する者さえいる。もちろん、そんな方々ばかりではないが、とくに駆け出しの外科専攻医の方々には、これから本書の内容に進む前に一番大事なメッセージをはっきりと記しておきたい。「この質問にどう答えるかが、あなたの外科医としての成功にかかっている」ということを。これは本書が一貫してあなたにお伝えしたいメッセージなのである。
専攻医になりたてのうちは簡単な手術から経験を積むことになるが、病状が軽く体格にも恵まれた好都合な手術ばかりをやっていても、一人前の外科医には“近づくことすら”できないのである。例えていうと、スライムばかり倒していても(理論的には)レベル40に到達できるかもしれないが、それは逆に遠回りだということである。簡単な手術をたくさん回してもらって満足していてはいけない。少しでも難易度の高い症例を受け持たせてもらえるよう努力することが、一人前の外科医への近道なのである。

では、「これはちょっと大変そうだけれど、君になら任せてもいいだろう」と言われるようになるために、どうやって周囲の信頼を勝ち得ていくのだろうか。それを考えて考え抜くことこそが、外科研修なのであり、毎日我々は試され、評価されているのである。手術のチャンスを得るためには、どうしても解剖の理解や手術場での動き、糸結びなどの手際をアピールしたくなるものである。しかしそれだけでは、いつまでたっても簡単な手術しか回ってこないのである。「キラリ」と光る術後管理こそが、他者に信頼される外科医として、重要な必要条件である。その点において、一日の始まり、朝一番のコミュニケーションは、外科医の運命を決定づける試練の場なのだ。
本書では、若手外科医が難易度の高い手術の術者を任されるための4つの原則を呈示したい。
朝は忙しい。報告する患者の優先順位を明確にせよ。
手術には段取りというものがある。この段取りが何より大事である。「すわ、緊急手術だ!」という事態に、のんびりと術式の詳細を議論している時間はない。何が律速段階なのかを計算し、準備しながら考えるのである。遠方の家族への連絡か、麻酔科医へか、手術室看護師へか、はたまた外科の上司へか、状況はそれぞれあるだろうから、すぐに動き出さなければならない。手術中も同様であろう。止血すべきか、切除すべきか、別の方向から攻めるべきか、今何をすべきかを常に多面的に考え、数ある選択肢の優先順位を決定し決断をし続けることこそが、外科医の役割であり、それができない者に術者の資格はない。待機的手術において、その差はさらに顕著になる。術前検査が十分でなければ、術式選択を誤ることになるし、道具の準備ができていなければ、手術は一向に始まらない。スムーズに開腹ができない者には次の手技を教える時間が減っていく。臨床業務とは底なしであり、細かいことをやり始めれば延々と仕事は終わらないから、限りある時間で仕事をするためには、とにかく優先順位をつける能力が必要である。
「尿量が少ないんです。」
「ふーん、だから何?」
「いえ、補液を増やして良いものか、一応許可を得ようかと。」
「何が言いたいのかよくわからないなぁ。INが少ないの? 血管内脱水なの? 血圧が低いの? ドレーンからの排液多いの?」
と一つ一つ聞かれてやっと考え始める。結局、それって朝一番で報告すべきことだったのだろうか。上司のイライラは募るばかりである。なぜなら、もっと優先して伝えるべきことがあることを知っているからだ。
外科医の朝は忙しい。超重症者や術後1日目の患者を第一に報告し、問題があれば、定時の手術が始まる前に手を打たなければならない。順調に経過している患者の報告に、時間をかける必要はない。
自分の目で見たことを報告せよ
優先順位の判断力を養うために重要なことは、自分の五感で緊急性を感じ取るということに尽きる。術前検査を自分の目で確認しない外科医は信頼できるだろうか。止血の際に出血点を自分の目で確認せず、闇雲に焼いたり縫ったりするのは愚策であろう。大切なことは自分の目で診て手で触れた感覚を研ぎ澄ますことなのである。これは手術中だけでなく、術後管理においても全く同じことが言える。
「硬膜外が切れたのか、かなり痛がっています」などナースから聞けるような報告には全く価値がない。通常の創痛の範疇を超える痛みなのかどうか、どこをどのくらい痛がっているのか、原因は何なのか、要するに「朝一番に対応すべき優先順位の高い事態なのか」を自分の目で診て、手で触って判断するのが、外科医の仕事なのである。存外、導尿カテーテルの痛みであったり、もともとの腰痛が悪化した場合であったり、あきらかに想定外の腹膜炎を発症していたりすることもある。「ちょっと痛がりさんなんですよね」などと談笑したり、ノロノロと鎮痛薬を処方している暇などないのである。
術後早期には疼痛だけでなく、発熱や尿量減少など、様々なトラブルが発生する。その多くは専攻医レベルで対処が可能なものであろう。念のため、なるべく多くの事象を上司に報告するという姿勢は、リスクマネジメントという点より理解できるが、情報には専門的解釈が加わって初めて価値が出るのである。ただ現象を羅列し、何が言いたいのかわからない報告を延々と聞くほどつらいことはないし、結局、何のリスクマネジメントにもならない。自分が何を心配しているのか分かるように報告することが第一歩であり、それがないとその次の段階として、現象をどのように病態生理学的に理解するかという議論に進むことができないのだ。
「おそらく大丈夫だと思いますが云々」と報告した時に、「うんうん、それは大丈夫そうだね」と流してもらえるか。もしくは「ちょっとおかしいんですよ、検査を追加しようと思うのですが」と報告した時に、「確かにそれはおかしいね、ちょっと一緒に診に行こうか」と言ってもらえるか。説得力のある説明ができるかどうかは、要するに自分の目で診たことを自分の言葉で伝えようとしているかということに尽きる。「術後5日目に発熱したので採血とCTを」などと言う前に、必ず身体所見から熱源を推定するという基本を怠ってはならない。CTをオーダーした後に、同僚に末梢ラインの刺入部の腫脹を発見され、しばらく冷たーい視線を浴びるということのなきよう、肝に銘じておきたい。
術野を思い出し、術後経過とリンクさせて病態を説明せよ
「ドレーン排液の量が多いので、まだドレーンを抜かない方がいいですか?」という質問はしばしば聞かれるが、「では、なぜこの患者のドレーン排液量は多いのか?」と切り返してみる。すると回答に詰まる者が実に多い(←いや、ちょっとは考えてくれ)。「多いから待つのか、多くても抜くのか」、その判断を知りたいのならば、当然「なぜ、この患者は(他の患者と違って)排液量が多いのか」という病態生理に思いが至らなければならないであろう。それが自明の理というものだ。しかし悲しいかな、忙しい業務に埋没し、思考停止してしまった専攻医は「ドレーンを抜くか抜かないか、どちらか決めて早く教えてくれ」という強迫観念にも似た心理状況から、このような愚問を発してしまうのである。
そのような時、一度目をつぶって耳を澄ましてみると、天の声が聞こえてくる。「迷ったら、術野を思い出せ」という声である。「そういえば、この患者さんの手術の時、術野ってどんな感じだっただろうか」と思い起こしてみるのである。開腹所見には、とくに腹水はなかったはずだ。癌の播種もなかったな。いや待てよ、手術中は術野にリンパ液の漏出が多くて吸引が大変だったではないか? 術前検査には引っかからなかったが、肝硬変がかなり進んでいたように見えたぞ……。このようなヒントが、必ず術野にあったはずなのだ。その情報と術後の病態がリンクして見えてくるか・こないかということだ。肝硬変による腹水がドレーンから出てくるとしたら、漫然とドレナージを続ける必要はない。むしろ利尿薬を使った方がよい。では、アルブミン値や尿量はどうかと、パズルのピースが少しずつ埋まってくるように病態が浮き出てくるではないか。
「えっ、病棟が忙しくて、その手術を見ていなかったから分からないって!?」 まぁ、ありがちだが、要するにそういうことなのである。術後管理をしっかりやろうと思ったら、当然手術をしっかり見ていないといけない。手術を見ていない者は、術後管理もできないのである。また、術後管理ができないうちは、手術を見に行く時間もなくなる。そのアリ地獄の中で、外科医はもがき苦しんできたのである。術野を目に焼き付けておくのだ! そして、術後経過と術野の画像を頭の中でリンクさせるのだ! そうすれば、おのずと手術の成績も向上するはずなのである。今日は病棟番だって!? そこをうまくやんなよ。それもあなたの実力のうちなのだ。
術者の立場に立って、困難に対峙せよ
多分に観念的になってしまうが、術者の心理を慮ることが術者への近道である。「自分が術者だったら、どう考えるかな」という視点である。いやいや、その反論は百も承知である。指導医である術者と同じレベルで考えられるようになるなどと、安易に言えたものではない。いったい何年かかるのか。それが一朝一夕にできれば、苦労はしないのである。しかし、ここで強調したいのは、当事者意識をアピールせよということである。普通の術者は、自分の手術が終わった後、少なからず合併症の発生を恐れているものだ。いくら経験豊富な指導医であっても、一例一例が大切な患者であり、真剣勝負なのだ。「この症例は簡単そうだから大丈夫」「俺はうまいから大丈夫」などの慢心こそが、合併症発生の最大のリスクであると信じている者も多い。いわば、“手術の神様に見放される”のを恐れているのである。手術は運の要素も強い。普段なら何の問題もない手技が、ことごとく裏目に出ることもある。外科医はそういう運を引き寄せるためにも、手術を神聖なものとし、真摯な気持ちで取り組もうとするのである。術直前には、個人個人でお決まりの儀式をしていたり(例えば、使うロッカーの位置を決めている、決まったトイレの個室に入る、梅シバを食べるなど)、合併症発生が続いた時には、お祓いに出かけたりする外科医を見たことはないだろうか。いや、ないとすれば観察力が足りないのである。あのドクターX・大門未知子先生だって、手術後には必ず患者の胸に手を当てていたではないか。あれも一種の儀式であろう。
これは大丈夫だと確信できる手術であっても、当事者はドキドキ・ハラハラしているものなのだ。それは、かつてあなたが国家試験の合格者番号欄に目を滑らせた瞬間の気持ちを思い出してもらってもよいし、漁に出た父親の無事を祈る家族の気持ちや、はたまた「ハハ キトク スグカエレ」という電報を手に汽車を待つ息子の心境に思いを馳せることでもよい。要するに、術者の立場に立つということは、神に祈るほどの気持ちで手術に対峙するということに他ならない。これまで述べてきたように、自分の目で診て、手で触って情報をとり、手術と術後経過の病態を十分に洞察したならば、最後は術者になった心持ちで対応策を決定するのである。「まあ、たぶん大丈夫だろう」「いつも、そうしている」「うまくいくに決まっている」。そういうチームの構成者が持つ、第三者的な慢心と言おうか、無責任と言おうか、それを術者は敏感に感じ取って、孤独感に苛まれているものなのである。
冒頭の朝の一コマのやり取りには、外科医としてのエッセンスが詰まっている。せっかくのアピールの場をどう活用しチャンスを生み出すか。繰り返しになるが、手術の上達につなげる意識を持って、周術期管理について深く洞察することが外科医への第一歩なのである。
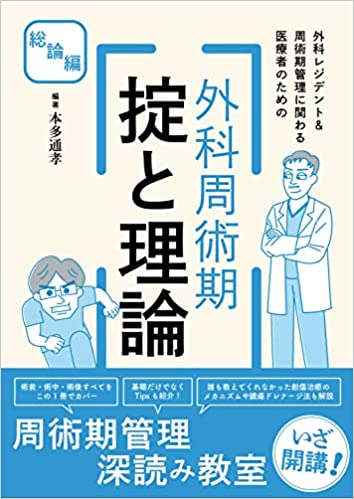

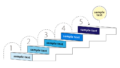

コメント