今や臨床研究を学ぶための教材は、書籍だけでもたくさんあり、自分に合ったものを探すのも一苦労です。今この記事を読んでいる方の多くは、働きながら臨床研究をしようと考えている方で、きっと、臨床研究のために費やせる時間も限られていると思います。
この記事では、医師12年目の私(河村)が、7年前に臨床研究を独学で始めた頃を思い出し、これから臨床研究を始めようとしている方、今まさに手探りで臨床研究に取り組んでいる方に向けて、是非読んでおくべき、持っておくべきだと思う本3選をご紹介したいと思います。
こんな人に読んでもらいたい!
- これから臨床研究を始めたいけど、何から始めたらいいか、わからない人
- 臨床研究は始めたけど、行き詰まっている人
臨床研究の道標

タイトルの通り、臨床研究の道標となる名著です。7つのステップとして、日常の臨床疑問を構造化することから始まり、英語論文発表までどのように研究を進めていくのかを対話形式で楽しく学ぶことができます。初学者にもわかる安易な言葉で記載されており、文量もそれほど多くないので、臨床研究を始める方の最初の一冊としておすすめです。臨床研究を始める前に、まずは読み物として、最初から最後まで読むというのがいいと思います。その後、この本に従って、研究計画を立ててみてください。初学者が抱える悩みとして、学会発表はできるけど、英語論文が書けないということがあります。そういった方は「臨床研究の迷子」にならないためにも、ぜひこの道標に沿って取り組んでみてください。また、一通り臨床研究をやってみたが、次のステップに進めないという方にもおすすめです。行き詰まってしまった時にこの本を開くと、最初に読んだ時とは違う気付きがあるし、「結局、臨床研究の一番大事なところは、ここなんだよな。」という部分が再確認できます。
なぜあなたの研究は進まないのか?

キャッチーなタイトルに惹かれる方も多いと思います。その中身は名言であふれています。著者の佐藤先生は、移植医療の最前線で活躍する超多忙な外科医です。第一線の臨床医が「何のために研究をするのか」といった根源的な話から、研究仮説の立て方、完遂するためのエッセンスなど臨床研究を含めあらゆる研究に共通するノウハウがまとめられています。何よりこの本は、一流の臨床医が書いたということで、現場で働く若手医師のモチベーションを刺激してくれます。研究は楽しいことも、つらいこともたくさんあります。つらくなった時、何のためにこんなことをやっているかわからなくなった時に、是非読んでほしいです。Q&A形式になっているので、興味のある項目を見つけて、その部分を読むだけでも、十分あなたのモチベーションを爆上げするでしょう。
臨床研究の教科書
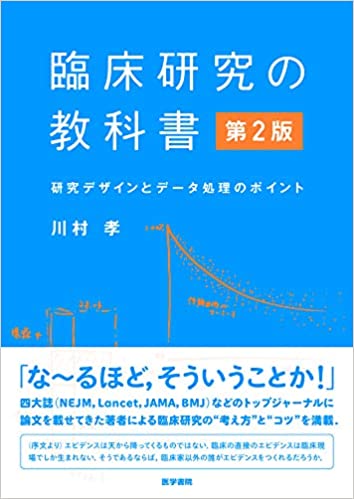
この本は、京大MCRコースの担当教授であった川村孝先生が、ご自身の研究および教育の経験を踏まえて実際の事例をもとに研究立案から論文作成までの一通りの方法論を解説してくれています。研究の立案から、統計解析手法、論文で使う英語のお作法まで多岐にわたる内容ですが、すべてがコンパクトかつ、的確にまとめられています。初学者が抱く疑問は、たいていこの本を読めば、ヒントがもらえます。疑問点があったら、すぐこの本で調べてみるという辞書的な使い方がおすすめです。ぜひ初学者が手元に置いておきたい1冊です。
(文責:河村英恭)



コメント