簡単な自己紹介
私は医師12年目の外科医で、臨床をしながら、臨床研究を続けてきました。臨床面では、各種専門医(消化器外科専門医、内視鏡外科技術認定医…)を所得し、研究面では、MPH(Master of public health)を取得し、PubMed掲載の英語論文18本(筆頭5本、共著13本)に携わってきました。外科医としても、研究者としても、中堅といったところでしょうか(気持ちはまだまだ若手です!)。はじめて論文を作成した時の苦労や、アクセプトされた時の喜びは、昨日のことのように覚えています。そんな私が、臨床研究初学者に近い目線で、臨床研究に関する有益な情報をお伝えしていけたらと思います。
この記事では、私の初めて出版された英語論文を紹介します。
今回は、私の初めて出版された英語論文に関する研究概要、出版に至るまでの経緯を紹介します。そこからアクセプトに至った要因を考察し、初めての英語論文を出版するために必要なものをご紹介したいと思います。
結論から言うと、初めての英語論文を出版するためにまず必要なもの、それは、
指導者、データ、時間
の3つです。
それでは、早速論文紹介に行ってみましょう!
- Kawamura H, Yamaguchi T, Yano Y, Hozumi T, Takaki Y, Matsumoto H, Nakano D, Takahashi K. Characteristics and Prognostic Factors of Bone Metastasis in Patients With Colorectal Cancer. Dis Colon Rectum. 2018;61(6):673-8. DOI: 10.1097/DCR.0000000000001071 PMID: 29722726
論文の概要
背景:悪性腫瘍の骨転移は、疼痛などの多彩な症状を引き起こし、QOL低下や予後不良につながります。しかし、大腸癌の骨転移は稀で症例集積が困難なため、臨床像は不明な点が多いです。そこで、大腸癌骨転移症例の臨床的特徴と予後因子を調査しました。
方法:研究デザインは単施設のRetrospectiveの観察研究(カルテを見返してデータ収集する研究)です。大腸癌骨転移症例104例を集め、主要アウトカムを全生存期間としました。
結果:骨転移部位は脊椎転移が最も多く、脊椎転移は左側結腸癌と関連がありました。生存期間中央値は5カ月で、予後不良因子は、2臓器以上の骨転移以外の遠隔臓器転移、高カルシウム血症、病的骨折でした。
結論:大腸癌骨転移は予後不良で、予後不良因子は2臓器以上の骨転移以外の遠隔臓器転移、高カルシウム血症、病的骨折です。大腸癌占拠部位と骨転移様式には関連があるかもしれません。
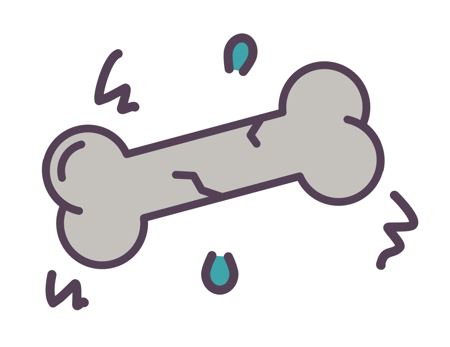
研究の裏側
きっかけは後輩の学会発表指導
この研究を始めたのは、私が医師6年目の頃で、上司T先生から、後期研修医Y先生の学会発表指導を頼まれたのがきっかけでした。翌年の消化器外科学会発表に向けて、データ収集、抄録作成、学会発表までを指導するように言われました。研究テーマはT先生がすでに用意してくれていた「大腸癌の骨転移」で、自施設の大腸癌骨転移症例リストと参考文献を渡されました。
当時の私は、後期研修医が終了し、臨床面では、後期研修医を指導する立場にありました。臨床研究はというと、50例くらいの症例のデータを使って、学会発表を4、5回したことがある程度で、論文童貞でした(日本語症例報告論文すら書いたことがありませんでした)。今振り返ると、後期研修医の学会発表指導を引き受けることは、無謀なことだったと思います。しかし、何かと先輩面をしたかった私は、この話を引き受けることにしました。
学会発表から論文作成へ
参考文献を元に、研究に必要と思われる項目をリストアップし、Y先生と一緒にデータを収集し、データシートを作成しました。解析は私が担当し、解析結果をY先生が抄録にまとめ、それを私がチェックし、T先生に見てもらうという流れで、抄録を提出しました。無事、抄録が採択され、の消化器外科学会でY先生が無事発表することができました。めでたし、めでたし…
と思っていたら、学会直後に、T先生から、「発表内容を論文化してみては?」という提案をいただきました。Y先生は学会発表を終え、すでにお腹いっぱいだったようで、スライド式で、論文執筆は私が担当することになりました。この時、すでにこの研究を始めてから1年が経過していました。
論文アクセプトまでの道のり
表と図は学会発表時に作成したので、後は文章にまとめるだけなのですが、ここからがすごく苦労しました。なにせ日本語論文も書いたことがないし、英語は苦手、なかなか筆が進まず、時間だけがすぎていきました。そんな中、翌年から私が別病院に異動することが決まりました。T先生はそんな私に「異動する前までに、論文を雑誌に投稿できるところまで完成させるように!でないと、論文は書けないよ!」と言いました。そこからおしりに火が付き、やっとのことで論文を書き上げ、異動した直後くらいに雑誌に投稿できることができました。最初に投稿したのがDisease of Colon and Rectumという雑誌で、大腸疾患を扱うジャーナルとしてはそこそこメジャーなジャーナルでした。幸いにも、Major revisionで、修正を加えて、その年の秋に無事アクセプトされました。最終的に出版されたのは翌年の6月でした。
はじめての英語論文に必要なもの
この論文は、医師6年目から約2年半かけて、出版に至りました。今考えると、最初の論文にしては、比較的スムーズに論文出版まで至ったと思います。私が臨床研究を学ぶために京都大学公衆衛生大学院に行った際に、最初の授業で、偉い先生が「指導者、データ、時間があれば、論文は書ける」と話していました。今振り返ると、この研究は、指導者、データ、時間が揃っていました。
指導者

いい指導者とは、研究の全体像が見えていて、研究者が困っている時に適切なアドバイアスをくれる人だと思います。この研究の指導者T先生は、まず、テーマ、参考論文、症例一覧表を与え、研究に必要なアイデア、データをくれました。次に、学会発表の結果を見て、論文作成を目指すという目標設定をしてくれました。さらに、異動前に論文を完成させるようになどのアドバイスも適宜くれました。その他の英文校正、雑誌投稿など大変なことはやってくれました。当時の私は、T先生の課題を、無理難題と思い、鬼だなと思ったこともありました。しかし、今考えると、T先生はいい指導者だったと思います。
次に、いい指導者はどのように見つけたらいいのでしょうか?
私の場合、T先生が歩み寄ってきてくれたからラッキーでした。しかし、いい指導者を見つけるのは至難の業です。以下、いい指導者の目安を紹介したいと思います。
- 毎年学会発表している
- 筆頭著者として5本以上PubMed掲載英論文を執筆している
- 臨床研究に関する論文を執筆している
要は、コンスタントに研究を続けていて、それを論文という形にした経験がある人です。最後の臨床研究…という条件は、基礎研究と臨床研究は、少し違う部分もあるので、臨床研究の経験がある人が望ましいという意味です。
データ

臨床研究にはデータが必要です。多くの臨床研究初学者は、自施設のデータをカルテから抽出する、Retrospectiveな観察研究を最初に取り組むと思います。自施設から、どのようなデータが入手でき、そこからどのような研究ができるか、逆に、自分の臨床疑問を、自施設のデータで解決できるかということを、研究計画時点で考えないといけません。
今回の研究も、自施設のデータをカルテから抽出して実施しました。私は当時、東京都のがん診療の中核病院に勤務しており、日本で有数の大腸癌の診療施設でした。また、外科が大腸癌診療のほとんどの部分(手術は当然ながら、化学療法、緩和治療に至るまで)を担当していました。そして、科内で大腸癌症例の症例データベースを代々作っていました。以上のことから、大腸癌骨転移症例の抽出も比較的容易で、研究テーマも、私にとって比較的なじみがあるものでした。
また、後期研修医が終了し、施設での診療に慣れた自分の立場は、データ収集にも生かされたと思います。後期研修時、診療録や退院サマリーの仕事は膨大でした。それらを高速に処理できるようになっていたおかげで、データ収集時、必要なデータが、カルテ内のどこにあるかということが瞬時にわかりました。そして、後期研修医Y先生と一緒にデータ収集したということも、データの質の向上につながったと思います。どのようなデータが必要か二人で考え、データの入力法、変数の定義などを言語化することにより、データの誤分類を最小限にできたと思います。
このように、所属施設の個性を活かした研究テーマは、新規性がある研究につながる可能性があります。また、自分の立場を活かすことにより、データ取得の実現可能性を高めることができます。例えば、緊急手術が多い施設に所属しているのであれば、緊急手術に関するテーマで研究すると、いいデータが集められる可能性が高いです。後期研修医で、CVポート手術を任されているのであれば、CVポートに関する研究もおもしろいかもしれません。
時間

論文を書くには時間の確保が大切です。今回のように結果まで出ていても、初学者にとって、英語論文を書くのは一苦労です。論文の構成、論理的な文章の作成、適切な文献の引用、English writing、…、多方面に注意しながら、進めていく必要があります。最初は似たようなテーマの論文をマネをするのがいいと思いますが、それでも時間はかかります。日常診療が忙しく、空き時間の論文を書こうと思っても、そんな時間があれば睡眠時間、という若手外科医も多いでしょう。
今回の研究では、私は主に医師7年目の時に英語論文を書いたのですが、その頃は、病棟業務、緊急対応の負担も少なく、日勤業務以外の時間は比較的確保できました。その中で、毎日朝1時間くらい論文を書くための時間を作り、少しずつ論文作成を進めることができました。
若手外科医は、緊急手術や病棟の急変などで呼び出されることが多く、安定して自分の時間を確保するのは難しいと思います。しかし、そこは、時間のマネジメント能力と研究をやりとげるための強い気持ちgrit力が試されるところでもあります。
まとめ
いい研究をするためには、いい指導者を見つけ、データを確保し、時間をかけることが重要です。本ブラッシュアップコースに参加すれば、いい指導者は見つけられたようなものです。データの確保については、また、別講でお話したいと思います。しかし、最後の、時間の確保というのは、研究者だけでなく、全人類の悩みでもあります。ブラッシュアップコース、臨床研究を通して、マネジメント力、grit力も鍛えていただければと思います。
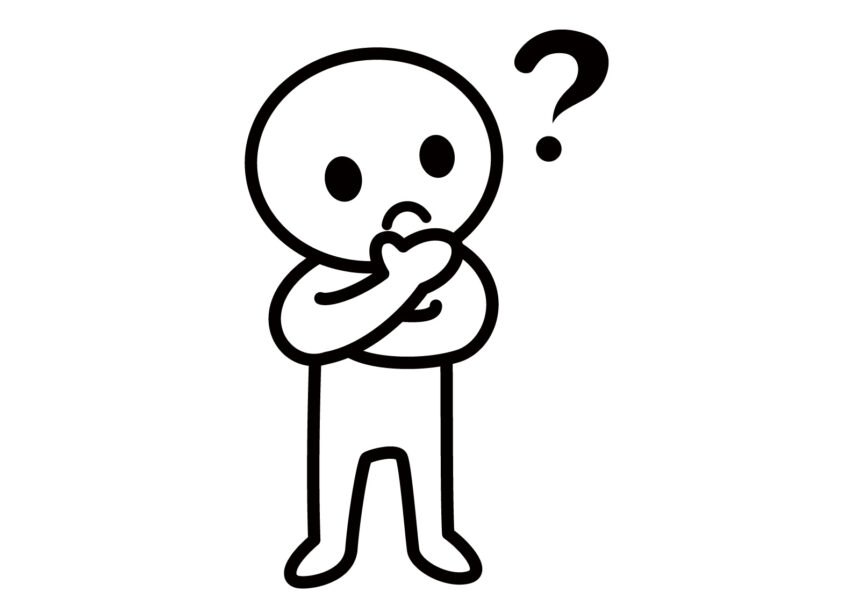
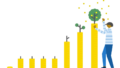

コメント